模試判定に振り回されるな。高2・高3のための“正しい見方”と振り返り術
こんにちは!JR城陽駅から徒歩1分の個別指導ゴーパスです。
今日は「模試の判定の正しい見方」と「振り返りのやり方」についてこれから受験学年になる2年生と真っ只中の3年生向けにはなしていきます。
私自身はこう思います。
判定は“目安”でしかなく、大事なのはこれからどうするかです!A〜Eに一喜一憂するより、点数の内訳の把握→原因追求→次の一手をどうするかを考えて実施できる人が伸びていきます。
確かに模試の合格判定は強いインパクトがあります。でも、その数秒の感情の揺れより、翌日からの具体的な勉強のほうが未来を変えます。
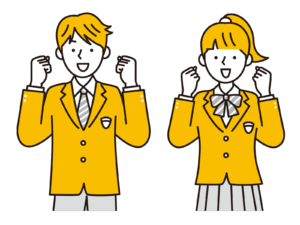
模試は受けた後が本番。ここから前半では、判定の仕組みと正しい見方/見るべきポイントまでを整理します。(後半で振り返りの手順を実践形式で解説します)
判定より“次の一手”。
こんな悩み、ありませんか?
- 進研模試はB判定なのに、全統模試はC判定⋯なんで?
- 「合格可能性40%」に気持ちを持っていかれて、勉強に戻れない。
- 直しをやろうとしても、どこから触れば点が伸びるのかが見えない。
今日の結論
- 判定はぶれるもの。A〜Cは入れ替わることがある。
- D・Eは“今は厳しい”シグナル。ただし“今は”です。
- いずれにせよ、点数の内訳を言語化して、次の一手(これからどうするか)を考えて実行するのみ。
なぜ振り返りが必要か
模試は“受けるだけ”だと、最高の参考書を買って袋のままにしているのと同じです。
模試を受けた時点での自分の出来るところ、解けなかったところや単元別の弱点が浮き彫りになっている最高の教材です。解説を活用して、出来なかった問題の理解や解き直し、今後の方針を立てることぐらいは全員必須です。
とくに全統模試(河合塾実施)は解説が詳しく、国語など一部科目は「市販できないくらい詳細」と言われるほど素晴らしい回もあります。
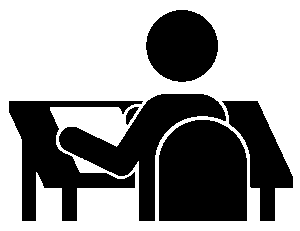
判定の仕組み、意味と捉え方
判定は“絶対基準”ではない
模試の判定は、予備校やリサーチ会社ごとに基準・母集団が違うため、同じ偏差値でも判定がズレます。
- 受験者層(母集団)の学力分布
- 問題の設計・配点
- 判定のカットラインの置き方
これらが異なるため、判定は普通に入れ替わると考えてOK。辛い判定が正しい/甘い判定が正しいという話でもありません。
A〜Eの“目安”を言い直す
- A判定:この方向性の勉強でOK。慢心せず、取りこぼしを拾う段階。
- B判定:得点力は高いがムラや穴がある。基礎再確認+科目ごとの苦手単元を強化。
- C判定:取るべき基本問題の取りこぼしがある。基礎の定着最優先+入試形式に合わせた練習を増やす。
- D以下:基礎・標準が未完成または時間内に解答し終えることが出来ていない。
「合格可能性○%」は鵜呑みにしない
本番は問題形式・傾向・時間配分が異なります。%は過去の統計×今回の受験者という“鏡像”でしかありません。数字や判定は受け止めつつも、本当にやるべきはどこで何点積むかという戦略づくりです。

予備校ごとの“出やすい判定”の傾向
ざっくりの並び
ベネッセ → 駿台・代ゼミ → 河合塾
右に行くほど、同じ偏差値でも判定が1〜2段階厳しめに出やすい大学・学部が多いように感じます。ただし繰り返しますが、これは正誤ではなく設計差。比較のための参考にとどめましょう。
この差をどう活かす?
- 一喜一憂しない:同じ会社の模試でも出題方針が違う回があります。
- 直近3回の“傾向”で見る:1回で浮かない・沈まない。移動平均で自分の流れを掴む。
- 厳しめの判定を“最低限ライン”に:悲観ではなく、準備の底を固めるための指標に。
模試で見るべきポイント
定点観測「何がどこまで身についたか」
- 範囲×設問タイプで把握:英語なら「語彙/文法/構文/長文(内容一致・要約・空所補充…)」
- できた/できないの二択で終わらせず、再現できた/運よく当たった/時間切れまでタグを付ける。
- 基礎の穴は最優先で塞ぐ。

得点の“捻出計画”
例:共テ英語
- 目標:次回95点 → 140点(+45)。
- 配点表を見ながら、大問3〜6の取りこぼし回収で+30、時間配分の最適化で+10、語彙の穴埋めで+5を捻出。
- さらに、長文の設問タイプ別テンプレを1日1タイプずつ練習。
→ 「どこで」+「何点上げるか」を先に決めると、やるべき勉強が自動的に決まる。
例:数学(数ⅠA・ⅡB)
- 目標:公式や解法のインプットで+20、計算精度アップで+10、図形や確率の定石で+10。
- ミス要因を定義忘れ/計算ミス/図形問題に分類。再現答案を書き直し“理由を言葉で説明”できるかチェック。
行動計画に落としこむ
- 教材:何で?(例:『シス単』『Vintage』『きめる!シリーズ』『黄色本』)
- 回数:何周/何回?(例:長文タイプ別10本×2周、大問3だけ10回)
- 締切:いつまで?(例:+72時間以内に“初回直し”完了、次回模試までに仕上げ)
模試振り返りのやり方
ゴールは次の一手を言えるまで
振り返りの目的はただ一つ。各科目で「何を・どれだけ・いつまでにやれば点が上がるか」を本人が言える状態にすること。
点数が悪くてもOKです。改善点が具体化→行動が決まる⇒⇒⇒勝ちです!

振り返り手順
模試当日—再現&感情メモ
- 再現答案:覚えている限りで、どこで迷い、どこで飛ばしたかを書き込む。
- 感情メモ:焦り/手応え/時間切れの瞬間などを一言で。熱が冷めないうちに。
原因タグ付け
3) 失点の原因タグを選ぶ:
- 知識不足(語彙・定義・公式)
- 判断ミス(設問の読み違い・根拠不十分)
- 時間配分(順序・粘りすぎ・飛ばし遅れ)
4) 配点×設問タイプで棚卸し:どこで何点落とし、どれがリカバリー可能だったか。
3日間以内に行動に起こす
5) 点の捻出計画を数値化:「次回+◯点」を大問・設問タイプに割り振る。
6) 教材×回数×締切に翻訳(例:大問3だけ10回/長文“空所補充”5本×2周/計算ドリル1日20問)
7) ルーティンに組み込む:学習カレンダーにそのまま貼る。
ここまでは確実に模試受験後3日以内にやってほしい項目です。
“当たり前”の質を問い直す
チェックリスト(YES/NOで)
- 復習は翌日・3日後・7日後など3回以上やっているか
- 参考書の用語・記号の意味を全て説明できるか(わからない語はその場で調べる)
- 音読→シャドーイングしているか(英語)
- 勉強を始める時間は固定されているか/
- 学習量は志望校の母数(上位◯万人)に見合っているか
- 直しは当日~3日以内に終えているか
- わからないことを放置していないか
迷ったら、“当たり前の基準”を1段上げる。基準が上がると、結果はあとから追いつきます。
よくある“詰まり”の外し方
- 難問ばかりをやってしまう→基礎の穴を埋めるまで難問禁止週間。
- 直しが長すぎて続かない→大問1つずつ絞って直し
- 時間が足りない→飛ばす勇気の練習(日常演習でも解かずに捨てる“撤退ライン”を決める)。
判定は目安、大切なのはこれから
模試が返されて、悩む気持ちはとてもわかります。
しかし、過去の自分の結果ですので過度に落ち込むのは厳禁。
課題分析と今後の計画を立てたらあとは前を向いて、これからどうやって何をいつ勉強していくかが大事です!前だけを向いてやっていきましょう!

