9月から間に合う!高3・浪人生の受験校・併願戦略
「まだ間に合うのか…」と不安になっているあなたへ
こんにちは!城陽駅から徒歩1分の個別指導ゴーパスです。
この記事にたどり着いたということは、こんな気持ちを抱えていませんか?
- 「受験校がなかなか決められないまま、もう9月…」
- 「併願校どうする?って言われても、どこがいいのかわからない」
- 「滑り止めを受けないなんて、甘い考えかな…」
焦り、迷い、不安あると思います。特に高校3年生や浪人生にとっては「決められないこと」自体がプレッシャーになります。
でも、安心してください!
9月からでも受験校戦略を立てることや併願校を考え直すことは可能です。
むしろこの時期だからこそ、冷静に選び直すことで、合格可能性も、進学後の納得感も、上げていけることもあります。
この記事では、以下のような人に向けて、「今からでも間に合う受験戦略」を、具体的にご提案していきます。
- 高3の9月を迎えても、進路が定まっていない方
- 第一志望は決めたものの、併願校・滑り止めが決まらずに困っている方
- 受験校選びを“なんとなく”で決めたくない方
あなたの迷いに、本気で応える内容をお届けします!

9月から“間に合う”受験戦略を立てる理由
3つの“戦略的選択”とは
早速本題へいきましょう。
受験勉強が中盤から終盤にさしかかるこの時期、逆転の可能性を高めるために必要なのは、闇雲な努力ではなく、次の3つの“戦略的選択”です。
① 大学のランクや偏差値で考える
「第一志望・第二志望・第三志望」が、偏差値の階層ごとにバランスよく並んでいるか?
自分の現在地(模試結果や過去問の結果)から“現実的に届くライン”を見極めることが合格率に直結します。
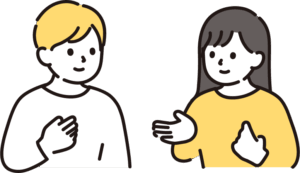
② 同じ大学でも“穴場学科”を狙う
第二志望大学であっても、学部・学科によっては大きく合格最低点が異なります。
「文学部でも真宗学科は入りやすい」など、出願戦略で合格ラインに差がつきます。
③ 滑り止めを受けない覚悟
「行きたくない大学には行かない」と決め、背水の陣を敷くことで本気モードにスイッチが入るタイプの人もいます。ただしこれは受験生本人のメンタル管理と家庭の理解も含めて慎重に考える必要があります。

このように、9月からの戦略には「やるべきこと」ではなく、“選ぶべきこと”があるのです。
だからこそ、この時期の選択は、今後の数ヵ月だけでなく、4月以降のあなたの納得感まで左右する大切な分岐点になります。
次の章では、多くの受験生が悩む「偏差値や大学ランクで考える受験戦略」について、具体的な例を交えて解説していきます。
受験校をランク・偏差値で分ける
関大→龍谷→佛教の偏差値階層モデル
多くの受験生が直面するのが、「第三志望をどう決めるか」問題です。
第一志望は自分の意思のみで決められる。第二志望も自然に決まる。
でも、第三志望や滑り止めとなると──
「どこまで下げれば“滑り止め”って言えるんだろう?」
「下げすぎると、行きたくないかも…でも安心はしたい…」
悩む気持ちや迷う気持ち、痛いほどわかります。
文系私大受験生の多くは偏差値で「階層化」して受験校を整理する考え方をしている人が多いのではないでしょうか。
たとえば、次のような構成があります:
| 志望段階 | 大学名 | 偏差値目安(一般選抜) |
|---|---|---|
| 第1志望 | 関西大学(経営・法・商など) | 55~60 |
| 第2志望 | 龍谷大学(経済・経営・法) | 45〜52.5 |
| 第3志望 | 佛教大学(社会・歴史) | 40〜47.5 |
(参考:パスナビの2025年度データベースより)
このように、偏差値が5~10毎に受験校を選定するのは、併願校を考えるうえで一番メジャーといえる方法です。
模試の結果では「第一志望はC〜D判定」「第二はB〜C」「第三はA判定」ぐらい、過去問演習時は第一志望は数回に1回、第二志望は2回に1回以上、第三志望校は確実に最低点を超えられる程度というのがバランスとして理想的ではないでしょうか。

次章では、この偏差値構造の考え方をもう一歩深めて、「第二志望大学の中にある“穴場学科”をどう活用するか?」という具体的な受験戦略をご紹介します。
第二志望大学で最低点が低い学科を受ける
龍谷大学文学部“真宗・仏教学科”
「龍谷大学=偏差値が高い」、名門大学有名大学であると感じている人も多いと思います。
皆さんの持っている印象通り、関西圏の受験生の多くが行きたいと願う大学の1つでレベルが高いです。一般選抜や公募推薦で受かる人は思われている以上に少ないでしょう。
しかし、同じ大学の中でも、合格最低点が低い学科=穴場学科が存在します。
代表例が、龍谷大学文学部の真宗学科・仏教学科です。
- 真宗学科:偏差値40
- 仏教学科:偏差値40
※2025年度パスナビ等のデータより推定
これらの学科は、いわゆる「専門性が高く、受験者が限定されがち」なため、倍率が下がりやすい傾向があります。
実際、合格最低点も全体平均より1割から2割低いケースも見られます。
併願戦略での使い方は?
龍谷大学を第二志望にする際、たとえば…
- 本命:社会学部 → 併願:文学部仏教学科
- 本命:法学部 → 併願:文学部真宗学科
という組み方をすると、同じ大学でも“偏差値差”を使った併願構成ができます。
さらに公募推薦や一般選抜での「同日併願」も可能であり、出願時にプラス1万円程度の追加受験料で済むこともあります。
併願の出願料・日程の注意点
穴場学科の活用には大きなメリットがありますが、出願設計には次の点に注意が必要です。
- 同じ大学内で複数学科を併願する場合、受験料が1〜2万円ずつ加算されることがあります。
- ただし、大学によっては「1学部併願割引」や「パック出願制度」があり、割安で複数学科を受けられるケースもあります。
- 同一日程の学部間併願ができるかどうかは、大学要項の細部まで確認が必須です。
第二志望大学内での“穴場活用”は、出願戦略として非常に効果的です。
偏差値だけに縛られず、大学ごとの学科構成を掘り下げていくことで、「合格できるチャンス」は広がります!

次章では、こうした「保険的な併願」を持たずに、滑り止めを捨てて挑む“背水の陣戦略”についてご紹介します。
滑り止めなし“背水の陣戦略”
行きたくない大学を切るという決断
併願校をどこにするか。それは「安全に合格する場所を確保すること」…だけではありません。
中には、
「絶対に行きたくない大学は、受けたくない」
「落ちたら浪人。それでもかまわない」と、滑り止めをあえて受けない、背水の陣を敷く受験生もいます。

背景には、単なる意地やプライドではなく、「本気で第一志望だけに集中したい」という強い意志や行きたくない大学なら受けなくていいという想いがあります。
合格することで生まれる「安心感」は、逆に言えば「気の緩み」や「妥協」にもなりかねません。
志望校しか受験しない。これは不合格リスクをかなり取った戦略です。
しかし、裏を返せば「絶対にここで決める!」という覚悟が受験勉強を加速させる」という効果もあるでしょう。私自身もそうでした。
背水の陣には、本気スイッチを押す力や、やらざる得ない環境や心意気を作り出すチカラがあるんです!
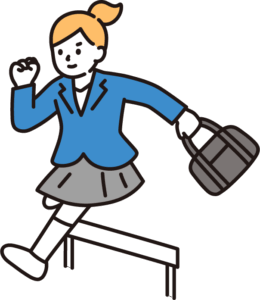
追い込む覚悟が合格力を生む:成功者の思考法
実際にこれまでも滑り止めを受けずに関関同立合格を果たした受験生を見てきました。
共通していたのは、次の3つの姿勢です。
- 「逃げ場がない」ことを受け入れた覚悟
→ 不安ではなく、「背水で行く」と自分で選んだ強さ。 - 第一志望以外の情報をシャットアウトし、徹底的に対策したこと
→ 過去問演習・配点分析・弱点対策を徹底。 - 合格することだけを考えて行動する
→ 「〇〇大学に受かるためにこの勉強でいいのか?」と毎日自問自答する
こうした生徒は、決して楽観的でも感情的でもありません。
むしろ、最も現実的に“勝つための行動”に集中できるタイプとも言えます。

背水の陣戦略は、“追い込み型”の人には非常にフィットする場合があります。
保護者との衝突を避ける「理解を得る伝え方」
ただし、「滑り止めを受けない」戦略は、受験生本人の気持ちだけでは完結しません。
とくに保護者の方にとっては、
「どこか受かっておいてくれないと、精神的に不安」
「浪人になるリスクを軽く見ないでほしい」
という気持ちがあるのも当然です。
だからこそ、伝え方に工夫が必要です。
- 「滑り止めを受けない=逃げ場を作らず、本気で戦うための選択」
- 「この3ヶ月、命をかけて準備する。その分、納得のいく報告ができるよう努力する」
- 「親に頼らず自分で判断し、自分の進路に責任を持つ」
こういった形で、“背水の陣=覚悟のある選択”であることを言葉で、行動で、背中で伝えていくことが大切です!
もしこの戦略を選ぶのであれば、それは“受けない自由”ではなく、“挑む責任”として引き受けてください。
今からできるチェックリストとアクション
第一〜第三志望校と併願学部を再確認する7つの問い
- 第一志望の合格ライン(偏差値・得点率)を把握できているか?
- 第二志望との偏差値差は10以上確保されているか?
- 第三志望は行ってもよいと思える大学か?
- 穴場学部や学科を併願校に加えているか?
- 出願スケジュールを“かぶらない順”で設計できているか?
- 入学金の支払額と時期を管理しているか?
- 家族と志望ライン・費用・進学後の生活について話せているか?
無料相談のご案内
迷ったら、相談しよう。迷ってからでは、出願できないから。
ゴーパスでは受験戦略の相談を受け付けています。
「第三志望どうしよう?」「穴場学科って実際どうなの?」
そんな悩みは、一緒に整理していくことでスッキリするかもしれません。
📩【今だけ】無料進路相談・出願戦略チェック 実施中
→ LINEでお気軽にご連絡ください。
