やってるのに成績が上がらない受験生へ|“努力の空回り”を止めるチェックリスト
こんにちは!JR城陽駅徒歩1分の個別指導塾、ゴーパスです。
「頑張ってるのに、なんで伸びないんだろう…」
「やってるのに結果が出ないのは、才能がないから…?」
そんなふうに悩んでいる受験生へ。
努力しているのに結果が出ないのは、「努力の中身」に原因があることがほとんどです。

ただやみくもに時間をかけても、自己流に頼っても、結果はついてきません。
大切なのは、「正しい方向に」「正しい強度で」努力できているかどうかです。
今回は、「やってるのに伸びない」受験生に共通する8つの落とし穴と、その改善策をチェックリスト形式でお届けします。
1つでも当てはまったら、そこが学力向上を止めているブレーキなのかもしれません。

なぜ“やってるのに伸びない”のか?——8つのチェックポイント
①わかったふり・わかったつもりになっている
「前にやったことがあるから大丈夫」
「解けると思います」。
そんな“わかったつもり”になっていませんか?
成績や学力が伸びない受験生の多くがこの「わかったふり」の罠にはまっています。
問題の解説を読んで「ああ、なるほど」と思えたからといって、それは“理解”ではなく“納得”です。
理解とは、「何も見ずに、自分の力だけで説明できる」「同じような問題に出くわしたときに正しく対応できる」こと。または理解できていなかったとしても問題を自力で解けるようになっていればOKです。
たとえば英語の文法問題で「この答えはBだよね?」と選んだものの、なぜBなのかは説明できない。
数学の問題で「公式を当てはめて解いたけど、そもそもなんでその公式が使えるのかはよくわからない」。こうした状態は“わかっていない”のと同じです。
この状態で勉強を積み重ねても、土台がグラグラなままなので、応用問題や実戦形式になると一気に崩れてしまいます。まずは「自分は本当に理解しているのか?」を問い直し、説明できるか、再現できるか、を必ず確認しましょう。
“解けた”ではなく“説明できる”が、真の理解のラインです。
②自己評価が高すぎる
模試の判定はC~D。
学校の定期テストでは平均点前後。
それでも「自分はやればできる」「たまたまミスしただけ」と思っていませんか?
この“根拠のない自信”こそ、成績が伸びない大きな原因の一つです。
もちろん自信を持つことは大切です。ですが、現実を直視しない“過信”は、正しい努力を邪魔します。
自己評価が高すぎる受験生ほど、間違いを分析しない。苦手から目を背ける。アドバイスを受け入れない。
結果、いつまでたっても同じ場所をぐるぐる回るだけ。成長のサイクルに入れません。

伸びる受験生は、自分の位置を冷静に見つめ、「何が足りないか」を考えて見つける力、それを受け入れる力を持っています。だから改善ができる。だから、伸びるんです。
点数や結果は、感情抜きの“現実”です。
目を背けず、データで自分を見る癖をつけましょう。
「自分はもっとできる」ではなく、「今の自分に何ができていて、何ができていないか」。
これに気づけるかどうかが、合否を分けます。
③素直ではない、アドバイスを聞き入れない
「わかってます」
「でも自分はこうしたいんで」
「このやり方が自分には合っています」
こんなセリフが口癖になっている人はいませんか?
それは、「アドバイスを聞いていない」のと同じです。話を聞いてません。
もちろん、自分の考えを持つのは悪いことではありません。
でも、結果が出ていないのに“我流”にこだわるのは、ただの自己満足。
たとえるなら、料理をしたことがない人がプロのレシピを無視して適当に味付けするようなものです。
結果は、想像どおり。うまくいかないでしょう。
受験も同じです。うまくいっていないなら「今のやり方」が間違っているかもしれない。
その前提で、信頼できる人のアドバイスを素直に受け入れる姿勢があるかどうか。

実際、ゴーパスでも「素直に実行できる子」は伸びるスピードが圧倒的に早いです。
勉強内容はもちろん、やり方・勉強の基準・優先順位・タイミング。
「自分では思いつかなかったこと」を取り入れた瞬間から、結果は動き始めます。
大事なのは、「言われたとおりにやること」ではありません。
アドバイスをもとに、よりよい形で自分の勉強に取り入れる力。
それが“本当の素直さ”であり、成長の原動力です。
④自己流のラクなやり方に逃げる
「このやり方のほうが自分には合っている」
「とりあえず今の方法で様子を見たい」
そう言って、なかなかやり方を変えられない受験生は意外と多いです。
しかし、その「自己流」は本当に成果が出るやり方でしょうか?
むしろ、「やりやすいから」「負担が少ないから」といった理由で、効果の薄いやり方にしがみついていないでしょうか?
たとえば——
- 英単語を覚えるときに2~3回書くだけ見るだけ
- 過去問演習が怖くて、復習ばかり繰り返している
- 得意科目や分野ばかり選んで勉強する
このように、「自己流」とは往々にして“無意識の逃げ”です。
頑張っているように見えて、実は本質的な課題と向き合っていないことも多いのです。
それではやっているだけで今の状況を良くしていくのは難しいでしょう。
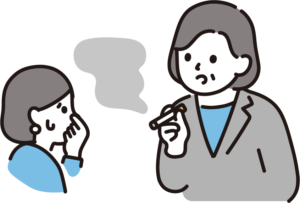
伸びていないなら勉強のやり方そのものを点検、検査する必要があります。
「目的」と「手段」がズレていないか?
時間とエネルギーを正しく使えているか?
この視点を持つだけでも、成績の伸び方は変わります。
本当に成果を出したいなら、自分にとって“きつい”ことにもあえて挑戦してみる。
それが、受験における「自己流の壁」を越える第一歩です!
⑤単位時間あたりの勉強量が少ない
「毎日5時間勉強してるのに、なんで成績が上がらないんだろう…」
「あいつよりやってるのに俺だけ上がらない」
そんな声をよく聞きます。でも、厳しいようですが——
「何時間やったか」よりも「その時間でどれだけ身につけたか」が重要なのです。
たとえば、同じ1時間でも…
- 1問ごとに思考を止めてしまい、ほとんど進まない
- ノートにきれいにまとめる作業に時間をかけすぎる
- 集中が途切れ、スマホや空想に時間を取られている
このような状態では、時間はかけても成果は出ません。
時間ばかり過ぎて結果はついてこないでしょう。
勉強時間に対して結果が出ていないと感じるなら1時間の勉強で何ページ進んだか、何問解いたか、何を記憶できたかを具体的に測ってみましょう。
そして、それを自分よりも勉強が出来る友人や、受験を突破してきた教師、塾のスタッフへぶつけてみてください。おそらく、時間に対しての学習量が少ないことを指摘されるでしょう。
そこから「時間」ではなく「成果」をベースに勉強の質を上げるトレーニングをすればいいんです。
また、集中力が持たない場合は「25分集中+5分休憩」のポモドーロ法や、勉強を小さく区切る戦略なども有効です。
時間をかけるだけでは足りません。「その1時間で何ができたか」にこだわることが、あなたには必要です!

⑥自己保身+言い訳は一流
「今日は部活が長引いたから…」
「体調が悪くて集中できなくて…」
「やろうとは思ってたんだけど…」
こうした言い訳、誰しも心当たりがあるのではないでしょうか。
でも、「できなかった理由」ではなく「どうすればできたか」を考える視点が、受験生にとっては何より重要です。
自己保身とは、「失敗や未達を他人や環境のせいにして、自分を守ろうとする態度」です。
その瞬間は楽かもしれませんが、原因を外に求め続ける限り、自分の成長は止まってしまいます。

こんな受験生がいました。
「先生の授業がわかりにくいからできない」と言っていた彼は、塾に来てから「どうすれば理解できるか」を自分で考えるようになりました。
すると、同じ授業でもノートの取り方や聞く姿勢が変わり、質問も自らするように。
文句ばかり言っていた生徒でしたが、先生のせいにすることをやめて、どうすればいいんだろうを問い続けて学力をあげていきました。
重要なのは、自分が変えられる部分に目を向けること。
言い訳を探す時間があれば、やれる方法を探しましょう。
その1歩1歩の積み重ねが、最終的な大逆転に直結します。
「うまくいかないときこそ、自分の成長チャンス」
そう捉えられる受験生こそ、本番で強いのです。
⑦被害者意識とやらされ感
「親がうるさいから仕方なく…」
「塾に通わされてるだけで、自分の意思じゃない」
「どうせやったって成績なんか変わらない」
そんな“やらされ感”や“被害者意識”を抱えたままでは、努力はなかなか実りません。
受験勉強(ほとんどのことに当てはまります)というのは、“自分ごと”になった瞬間から加速度的に伸びていきます。
逆に言えば、どれだけ勉強時間を積んでも、心の奥で「誰かのため」「仕方なく」という感覚が残っていると、伸び悩みます。
やらされ感や被害者意識を打破する第一歩は、「これは誰のための受験なのか?」と、自分に問い直すこと。
そして、環境や他人のせいにする前に、自分にとっての「意味」や「目標」を明確にすることです。

人に言われてやっている限り、いつか限界がきます。
でも、自分で決めた目標に向かって努力できる人は、多少の壁では折れません。
“やらされ勉強”を卒業し、**“自ら勝ち取りに行く受験”**へと意識を切り替えましょう。
⑧すぐにスマホを触って時間を溶かす
「5分だけ動画を見るつもりが、気づけば1時間…」
「勉強してたのに通知が鳴って集中が切れた」
「LINEを開いて、気づいたらSNSを巡回していた」
こうした“スマホによる時間の蒸発”は、受験生の最大の敵のひとつです。
どれだけやる気があっても、スマホが手元にあるだけで集中力は30〜50%も低下するという研究結果もあります。
これはもう、意思の強さではどうにもならない“構造的な問題”です。
だからこそ、「触らない仕組み」そのものを生活に組み込む必要があります。
以前のコラムでも詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
👉 参考:ゴーパス公式「スマホ断ち」記事
受験は、集中できる環境を作った人が勝ちます。
スマホを触らない自分を「正しい状態」にしてしまうこと。
それが、“本当に勉強している受験生”の第一条件です。
空回りから抜け出すために——今日から変えられること
努力が結果につながる人・つながらない人の違いとは?
「頑張っているのに、なぜ成績が伸びないんだろう?」
この問いに正面から向き合ったとき、見えてくるものがあります。
それは「正しい方向への努力」ができているかどうか。
今まで見てきた8つのチェックポイント。
どれか1つでも当てはまっていたなら、そこには伸びない原因があります。
でも逆に言えば、
その原因を見つけて修正すれば、あなたの努力は報われるということです。
完璧を目指すより、まず“ひとつ”変えることから
すべてを一気に直そうとしなくても構いません。
まずはひとつ、思い当たるところから改善してみてください。
たとえば、
「今日だけスマホを手の届かない場所に置いて勉強してみる」
「“わかったつもり”の問題を解き直してみる」
「アドバイスを一度、全部そのまま受け入れてやってみる」
その小さな変化が、やがて大きな変化を呼びます。
あなたの勉強は、ちゃんと“伸びる努力”に変えられるのです。
「できない理由」より「変える方法」を考えよう
勉強は、才能ではなく「修正と改善の積み重ね」です。
・「自分はダメだ」と思い込む前に、
・「やっているのに伸びない」と嘆く前に、
・「どうせ無理」と諦める前に——
“努力が空回りしない方法”を、今日から実践してみてください。
そして、もしあなたが一人でやるのが難しいと感じているなら、
私達がいつでもあなたの隣に立って、共に戦います。
